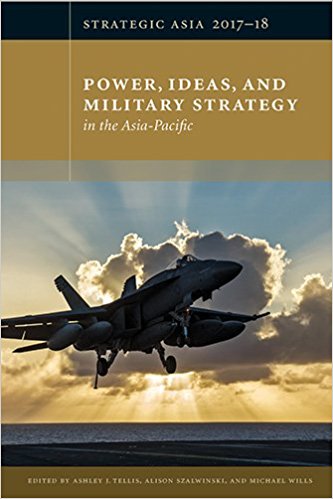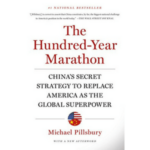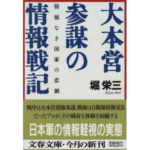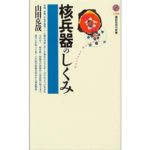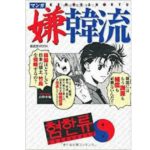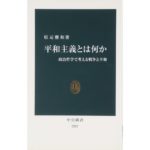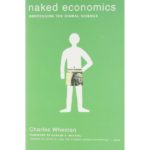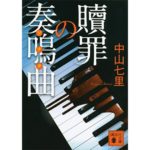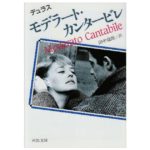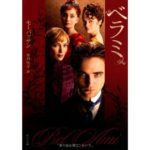専門書だけど割と楽しく読めてしまう
本書は、アメリカのNational Bureau of Asian Research という、アメリカにおけるアジア研究の重鎮ともいえるシンクタンクが、毎年12月に出している「Strategic Asia」というシリーズの最新作です。本シリーズは、米国大学院の東アジアに関する授業ではよく必読文献として出されており、米国における東アジア研究の基本文献の一つという位置づけになっている感があります。そういう意味で本シリーズは、東アジア安全保障についての知識が得られるだけでなく、米国の東アジアに関する一般的な視点を学べるという点でも有益だと思います。過去には、中国の軍事戦略、東アジアにおける核拡散の可能性、東アジアにおける「国力」についての考察など、様々な側面から東アジアの安全保障を分析しています。
さて、前置きがやたら長くなってしまい恐縮ですが(^^;)、本書はそんな「Strategic Asia」シリーズの最新作で、東アジアの主要国の軍事戦略を解説しています。中国、ロシア、日本、韓国、インド、インドネシア、そして米国について、それぞれの軍事戦略の概略がその分野の専門家によって論じられています。
この分野について予備知識があまりなくても、
・各国のおかれている現状がどのようなものか
・その現状に対して現在どのような戦略をとっており
・将来的にどのような戦略をとっていくのか
ということがわかりやすく解説されているため、理解するのは難しくないと思います。
本書を読み終えれば、東アジアの軍事的な側面について、幅広く、そして深い知識が得られる得られるのではないかと思います。
本書を読んで私が特に「なるほど!」と思ったのは、ロシアの軍事戦略についてでした。ロシアは近年では特にヨーロッパや米国を敵視した政策をとっており、今月(3月)にプーチン大統領が行った年次教書演説でも、ヨーロッパや米国などを対抗するためとみられる新兵器を多く発表しました。一方で、ロシアは中国に対しては蜜月関係を続けており、特段の脅威とみなしている向きはあまり感じられません。一見すると、中国は人口も多く、国境も広くロシアと隣接しており、また歴史的に見てもむしろロシアと仲の良かった時期のほうが珍しいため、ロシアが中国よりも西側諸国(古い?)を敵視している政策にちょっと疑問を持っておりました。
本書は私のそんな疑問点をすっきりと解消してくれました。一言で言うと、「中国からの脅威は物理的なもの(人口の多さ、強大な軍事力)であり、ロシアの政治体制を脅かす性質ではないが、西側諸国の脅威は価値観(民主主義など)にかかわるものであり、ロシアの政治体制を直接脅かす性質である」から、と指摘しています。このほかにもいろいろな知見がちりばめられており、専門書の割には楽しんで読み進めることができます。
東アジアに安全保障に興味のある方には、自信をもっておススメできるクオリティだと思います。難点は、日本での入手がやや難しいことです。日本のアマゾンでもまだ本書は見当たらず、さしあたり米国のAmazon等で入手する必要がありますが、そのような手間暇(&送料)をかけても入手する価値はアリだと思います。
Strategic Asia 2017-18: Power, Ideas, and Military Strategy in the Asia-Pacific
Ashley J. Tellis (著者兼編集)、Oriana Skylar Mastro (著者)、Mark N. Katz (著者)、他
夫
最新記事 by 夫 (全て見る)
- Naked Economics(経済学をまる裸にする):すべての経済オンチに贈る最高の入門書 - 2022年11月2日
- 平和主義とは何か:平和主義とは何か:冷静に平和主義を考えるために - 2020年2月14日
- 自分の時間:限られた時間で自分を高める方法 - 2020年2月7日